ポストエディットとは?翻訳との違い、AI時代の必須スキルを徹底解説

DeepLやChatGPTをはじめとする、高性能なAI翻訳(機械翻訳)が、誰でも手軽に使えるようになりました。その驚異的な進化を目の当たりにして、「もはや翻訳者の仕事はAIに奪われるのでは?」と感じたことがある方も少なくないでしょう。
しかし、ビジネスの現場では、全く逆の現象が起きています。それは、AIの「速さ・安さ」と、人間の「正確さ・表現力」を戦略的に組み合わせる、新しい翻訳手法「ポストエディット(Post-Edit)」の急速な普及です。
この記事では、AI時代の必須スキルともいえる「ポストエディット」とは一体何なのか、その基本的な定義から、具体的な手順、そしてビジネスにおける活用法まで、その全貌を徹底的に、そして分かりやすく解説します。
ポストエディット(MTPE)とは?機械翻訳を「完成」させる最後のひと手間
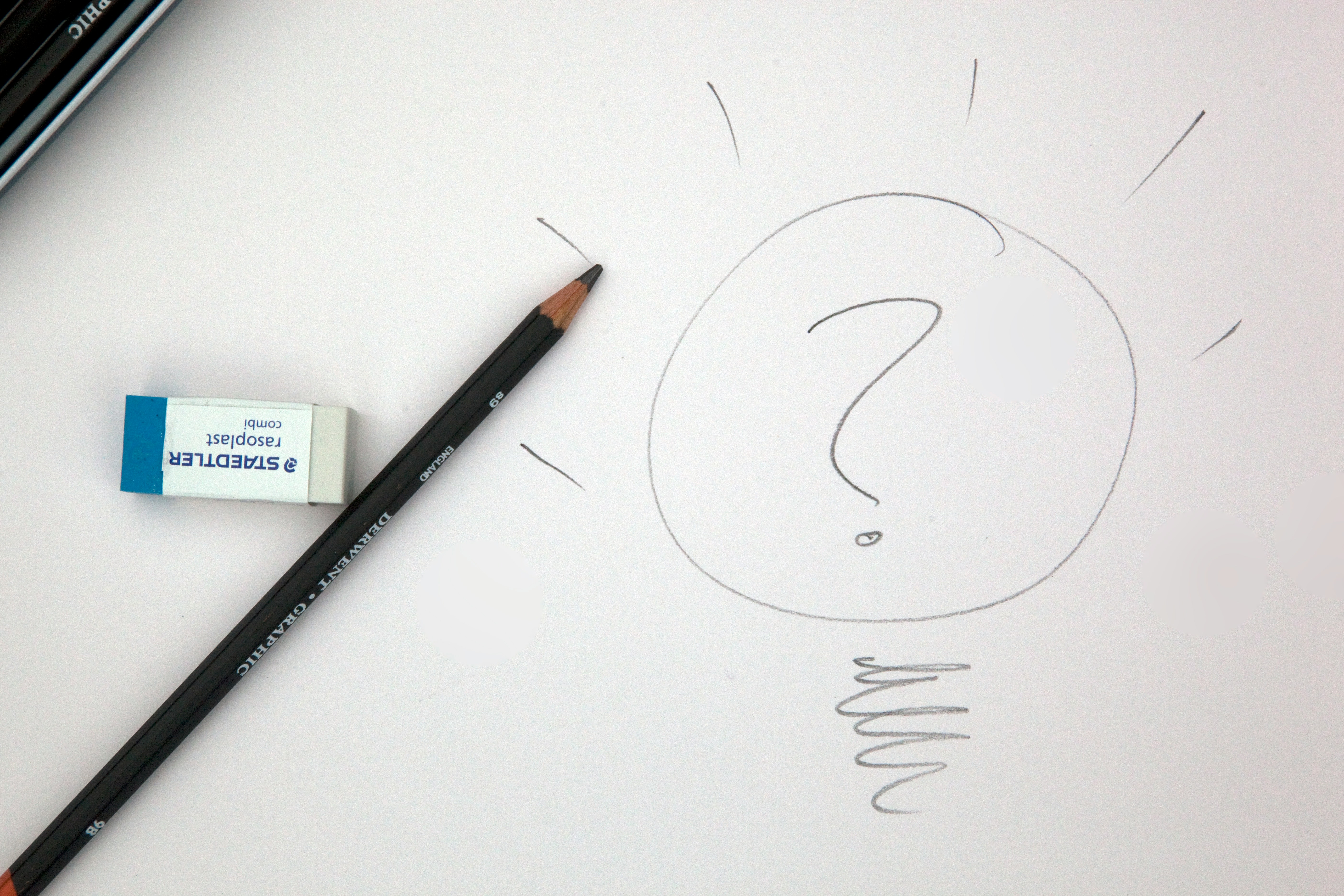
ポストエディットとは、AIなどの機械翻訳(MT: Machine Translation)が出力した訳文を、人間(ポストエディター)が修正・編集(Post-Edit)し、目的に応じた品質の文章に仕上げる作業のことです。その頭文字をとって「MTPE」とも呼ばれます。
例えるなら、AIが作成した翻訳文の「下書き」を、人間が「清書」して完璧な文章に仕上げていくプロセス、とイメージすると分かりやすいでしょう。
なぜ今、ポストエディットが注目されているのか?
ポストエディットという考え方自体は以前から存在しましたが、ここ数年で急速に注目度が高まっています。その最大の背景は、言うまでもなくAI翻訳の精度の飛躍的な向上です。
一昔前の機械翻訳は、単語を置き換えただけの、意味不明な文章を生成することも珍しくありませんでした。しかし、現在のAI翻訳は、文脈を理解し、非常に自然で正確な文章を生成できるようになっています。これにより、人間がゼロから翻訳するよりも、「まずAIに翻訳の下書きをさせて、人間がそれを修正・ブラッシュアップする」という進め方の方が、圧倒的に速く、安く、そして質の高い翻訳を実現できるようになったのです。
「人力翻訳」「機械翻訳」と何が違う?3つの翻訳手法を徹底比較
ポストエディットは、従来の「人力翻訳」と「機械翻訳」の中間に位置する、第3の選択肢です。それぞれの特徴を比較してみましょう。
品質・コスト・スピードのバランスを取る第3の選択肢
翻訳業務において常にトレードオフの関係にある「品質」「コスト」「スピード」の3要素。ポストエディットは、これらのバランスを、目的に応じて最適化するための、極めて現実的で賢い手法といえます。
各手法のメリット・デメリットがわかる比較表
手法 | 品質 | コスト | スピード | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
人力翻訳 | ◎ 最も高い | × 最も高い | × 最も遅い | 契約書、広告コピー、文学作品 |
ポストエディット (MTPE) | ○~◎ 調整可能 | ○ 中程度 | ○ 中程度 | マニュアル、Webサイト、社内文書 |
機械翻訳(MT)のまま | △~○ 不安定 | ◎ 最も安い | ◎ 最も速い | 内容の概要把握、個人的な利用 |
ポストエディットの目的と得られる3つの大きなメリット
では、企業がポストエディットを導入することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。それは、翻訳業務における生産性の劇的な向上に集約されます。
①翻訳コストの大幅な削減
ポストエディットは、翻訳者がゼロから翻訳する場合と比較して、作業時間を大幅に短縮できます。これにより、翻訳会社に外注する際の費用や、社内で翻訳作業を行う際の人件費を、ケースによっては半分以下にまで削減できる可能性があります。
②翻訳・公開までのリードタイム短縮
翻訳にかかる時間が短くなることは、ビジネスのスピードを加速させます。新製品の海外リリースや、重要な情報のWebサイトでの多言語公開など、これまで数週間かかっていた作業が数日で完了できるようになり、競合他社に先んじて市場にアプローチすることが可能になります。
③一定の品質を担保した上での大量翻訳の実現
製品マニュアル、ヘルプページのFAQ、過去のブログ記事など、従来はコストや時間の問題で多言語化を諦めていた、膨大な量のコンテンツ。ポストエディットを活用すれば、これら大量のコンテンツも、一定の品質を担保しながら、現実的なコストと期間で多言語化することが可能になるのです。
ポストエディットの2つの品質レベル|「ライト」と「フル」の違い
ポストエディットの作業は、常に同じではありません。翻訳するコンテンツの目的や、求められる品質に応じて、作業のレベルを柔軟に調整できるのが大きな特徴です。
ライトエディット:「意味が正確に伝わる」レベル
ライトエディットは、機械翻訳の出力結果に対して、明らかな誤訳や文法的な間違い、不適切な単語の選択など、読者が意味を理解する上で妨げとなる致命的なエラーのみを修正する作業です。訳文のスタイルや表現の細かな洗練さまでは追求せず、あくまで「意味が正確に、間違いなく伝わる」ことをゴールとします。
【適した用途】
- 社内向けの議事録や報告書
- 海外ニュースや競合情報の概要把握
- ユーザーレビューやSNSの投稿内容の翻訳
フルエディット:「人力翻訳と同等の完璧な」レベル
フルエディットは、ライトエディットの作業に加えて、用語の統一、文体(トーン&マナー)の調整、不自然な言い回しの修正、そしてターゲット市場の文化的な背景に合わせたニュアンスの調整まで行います。そのゴールは、人間がゼロから翻訳したものと遜色のない「出版可能なレベル」の完璧な品質です。
【適した用途】
- 企業の公式Webサイト
- カタログやパンフレットなどのマーケティング資料
- 製品マニュアル、プレスリリース
- 法的効力を持つ文書(※ただし、契約書などは人力翻訳が推奨される)
ポストエディターに求められるスキルとは?翻訳者との違い
.jpg)
ポストエディットを行う専門家を「ポストエディター」と呼びます。彼らは、従来の翻訳者とは少し異なる、特殊なスキルセットが求められます。
翻訳スキルに加えて必要な「機械翻訳のクセ」への理解
もちろん、原文と訳文の言語に精通している高度な翻訳スキルは必須です。それに加え、使用するAI翻訳エンジンが、どのような間違いをしやすいか(例:固有名詞を誤認識する、主語を取り違える、比喩表現を直訳してしまうなど)という「クセ」を熟知している必要があります。これにより、修正すべき箇所を効率的に見つけ出すことができるのです。
高い注意力と効率的な修正能力
ポストエディットは、ゼロから文章を創造する作業よりも、間違い探しのように原文と訳文を高速で比較し、誤りや不自然な点を見抜く高い注意力が求められます。そして、見つけた問題に対し、最小限の修正で、最も効果的に品質を高める効率的な編集・リライト能力も不可欠です。
ポストエディットの具体的な手順|3つのプロセス
質の高いポストエディットは、単に機械翻訳の結果を修正するだけではありません。実は、翻訳作業の「前」の準備段階が、最終的な品質と効率を大きく左右します。
① プリエディット(Pre-edit):機械翻訳しやすい原文に整える
プリエディットとは、機械翻訳にかける前の原文(日本語)を、AIが誤解しないように、あらかじめシンプルで分かりやすい文章に整える作業です。例えば、
- 一文を短く、シンプルにする。
- 曖昧な表現や、主語が省略された文章を明確にする。
- 「てにをは」を正しく使う。
といった一手間を加えるだけで、機械翻訳の精度は劇的に向上し、後のポストエディット作業の負担を大幅に軽減できます。
② 機械翻訳(MT):最適なエンジンで翻訳を実行する
次に、プリエディットした原文を、機械翻訳にかけます。DeepLやGoogle翻訳といった汎用的なエンジンだけでなく、特定の専門分野に特化したエンジンや、企業独自の用語集(辞書)を登録できる有料の翻訳ツールなどを活用し、コンテンツの特性に合った最適なエンジンを選択することが重要です。
③ ポストエディット(Post-edit):出力結果を修正・編集する
最後に出てきた機械翻訳の出力結果を、前述した「ライトエディット」または「フルエディット」の方針に基づき、人間(ポストエディター)が修正・編集していきます。この3つのプロセスを経て、ポストエディットは完了します。
ポストエディットが有効なコンテンツ、向かないコンテンツ
ポストエディットは万能ではありません。その特性を理解し、コンテンツの種類によって使い分けることが重要です。
【向いている】マニュアル、社内文書、Webサイト、FAQなど
ポストエディットが最も効果を発揮するのは、内容がある程度定型的で、情報伝達の正確性が重視される、大量のテキストです。具体的には、製品マニュアル、仕様書、社内規定、ヘルプページのFAQ、そして膨大なページ数を持つWebサイトのコンテンツなどが挙げられます。
【向かない】広告コピー、文学作品、ブランドメッセージなど
一方で、創造性や、人の感情に深く訴えかけるニュアンス、行間の意味が極めて重要なコンテンツには向いていません。例えば、企業のブランドイメージを決定づける広告のキャッチコピーや、文学作品、経営トップが発信する重要なメッセージなどは、AIを介さず、初めからプロの人間がその感性を最大限に活かして翻訳(トランスクリエーション)すべきでしょう。
【実践】Webサイトの多言語化におけるポストエディットの戦略的活用
数ある活用シーンの中でも、ポストエディットのメリットを最も活かせるのが「Webサイトの多言語化」です。
なぜWebサイトの多言語化とポストエディットは相性が良いのか
Webサイトは、製品情報から企業の理念、ブログ記事、お知らせ、お客様の声まで、膨大な量の、そして多様な性質のコンテンツで構成されています。これら全てを人力で翻訳するには、莫大なコストと時間がかかります。かといって、機械翻訳のまま公開するのは、企業の信頼性を大きく損ないます。品質、コスト、スピードのバランスが厳しく求められるWebサイトの多言語化は、まさにポストエディットの考え方が最も活きる領域なのです。
AI翻訳と人間のチェックを組み合わせた、効率的な運用フロー
例えば、「まずサイト全体をAIで自動翻訳し、即座に多言語公開する → トップページや製品紹介など、特に重要なマーケティングページのみ、プロによるフルエディットを依頼する → ブログ記事やFAQは、社内の担当者がライトエディットで随時品質を担保していく」といった、戦略的で効率的な運用フローを構築することが可能になります。
ポストエディット基盤を持つ「Autolingual」で効率的な多言語化を

「この理想的なWebサイトの翻訳ワークフローを、一つのツールで、専門知識なく実現したい」 その答えが、株式会社Enjuが提供するWebサイト多言語化サービス「Autolingual(オートリンガル)」です。
高品質なAI翻訳をベースに、ユーザー自身が簡単にポストエディット
Autolingualは、まず高品質なAI翻訳で、あなたのWebサイト全体を瞬時に多言語化します。そして、その翻訳結果を、管理画面上でサイトの見たまま、直感的に、そして簡単に修正・編集(ポストエディット)することができます。専門知識は一切不要で、誰でもポストエディターになることが可能です。
必要に応じてプロの翻訳者による「フルエディット」も依頼可能
自社での修正だけでは不安な、特に重要なページについては、管理画面からワンストップでプロのネイティブ翻訳者によるチェック(フルエディット)を依頼することもできます。これにより、「コストを抑えたいページは自分でライトエディット」「ブランドに関わるページはプロにフルエディット」といった、柔軟で戦略的な品質管理が実現します。
サイト全体の翻訳ワークフローを一つのツールで完結
Autolingualは、プリエディットの役割を果たす「辞書登録機能」から、ベースとなる「AI翻訳」、そして「セルフでのポストエディット」と「プロによるポストエディット」まで、これまで解説してきたポストエディットの翻訳ワークフローの全てを、一つのツールでシームレスに完結させることができるのです。
関連記事:
Webサイトの多言語化はこうやる!言語切り替えボタンの実装について
まとめ
本記事では、「ポストエディット」について、その基本的な意味から、具体的な手法、そしてビジネスにおける戦略的な活用法までを、体系的に解説しました。
ポストエディットは、AI翻訳の進化が生んだ、AIと人間が協働するための、新しい時代の翻訳手法です。それは、翻訳の「品質」「コスト」「スピード」という永遠の課題に対し、バランスの取れた現実的な解を提供する、極めて賢明な選択肢といえるでしょう。
特に、膨大な情報量を持ち、継続的な更新が求められるWebサイトの多言語化において、ポストエディットの考え方は絶大な効果を発揮します。
「Autolingual」のようなツールを賢く活用すれば、これまで専門家のものであった高度な翻訳ワークフローを、誰でも、そして今日から自社のものにすることができます。この記事が、あなたのビジネスのグローバルな情報発信を、新たなステージへと引き上げる一助となれば幸いです。